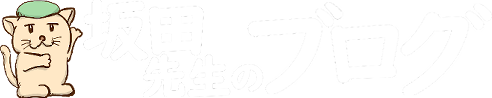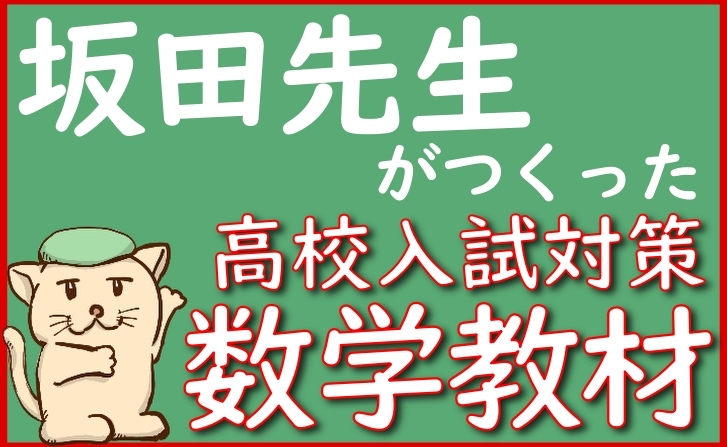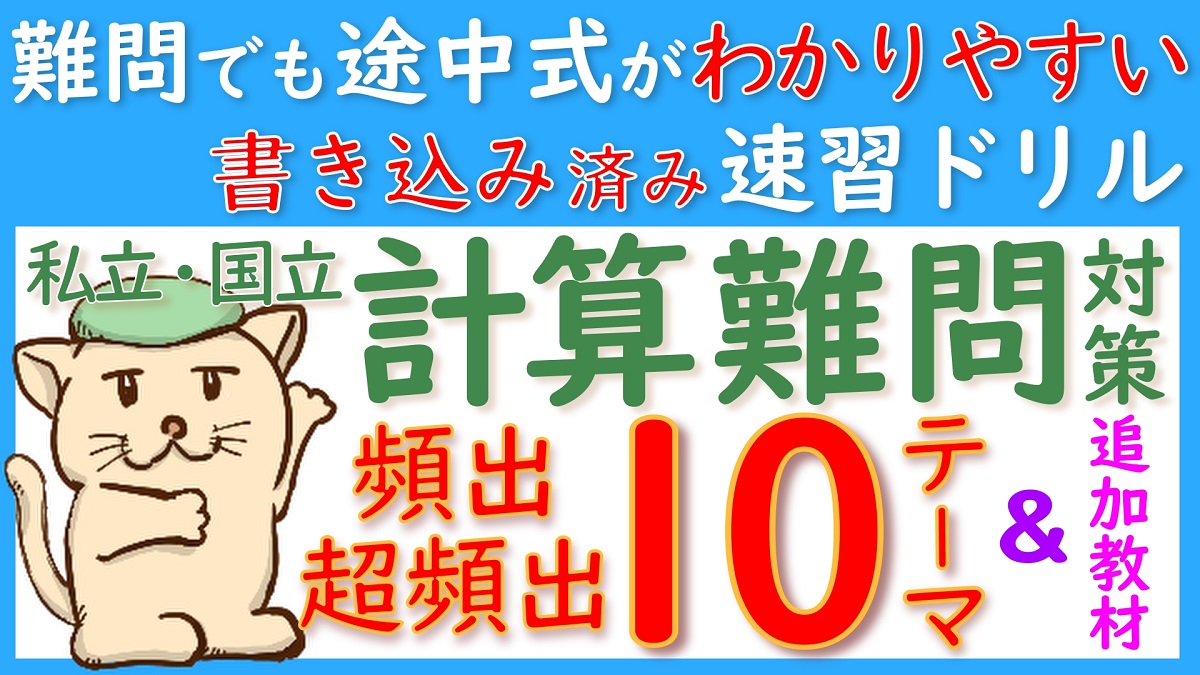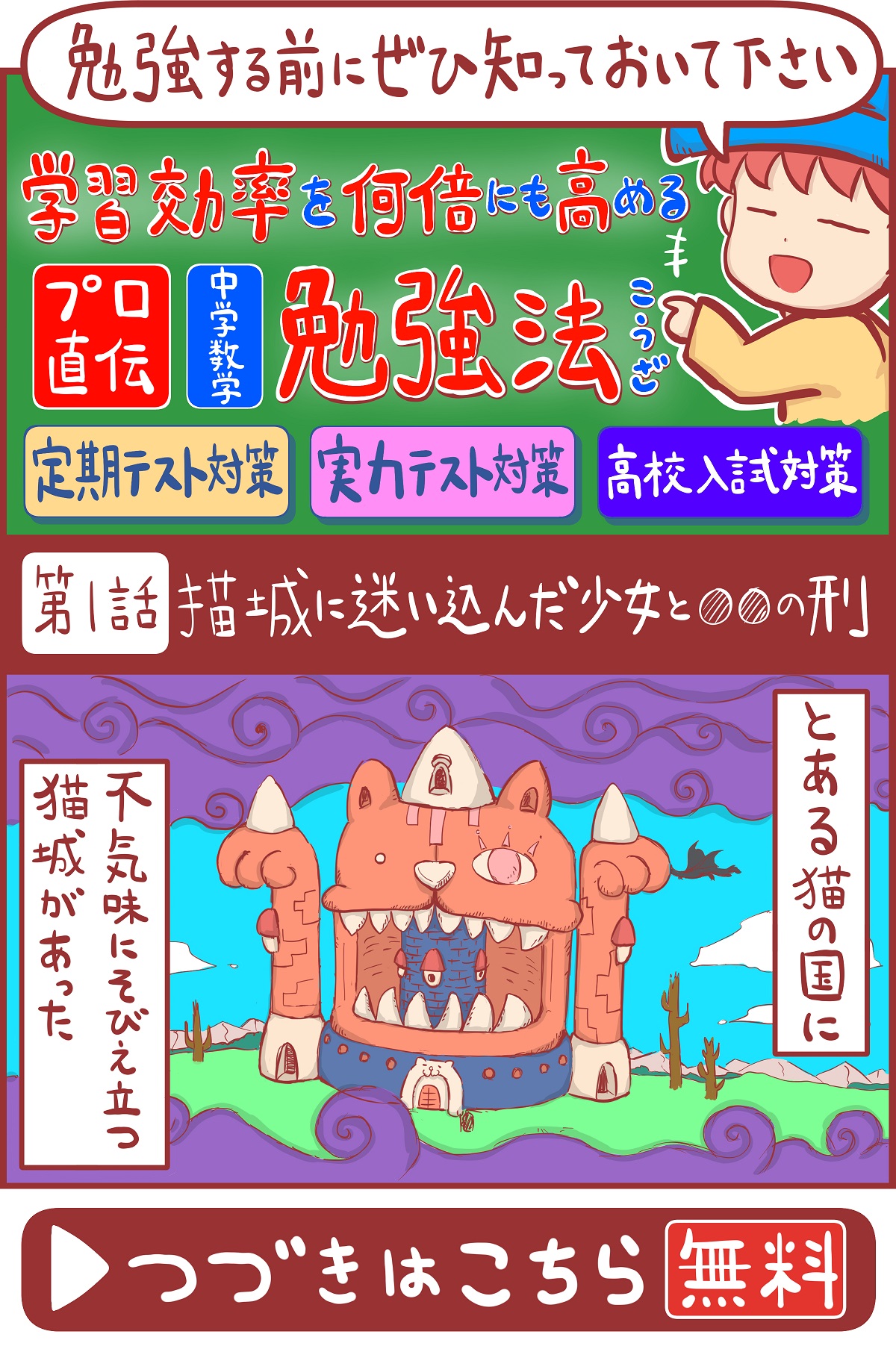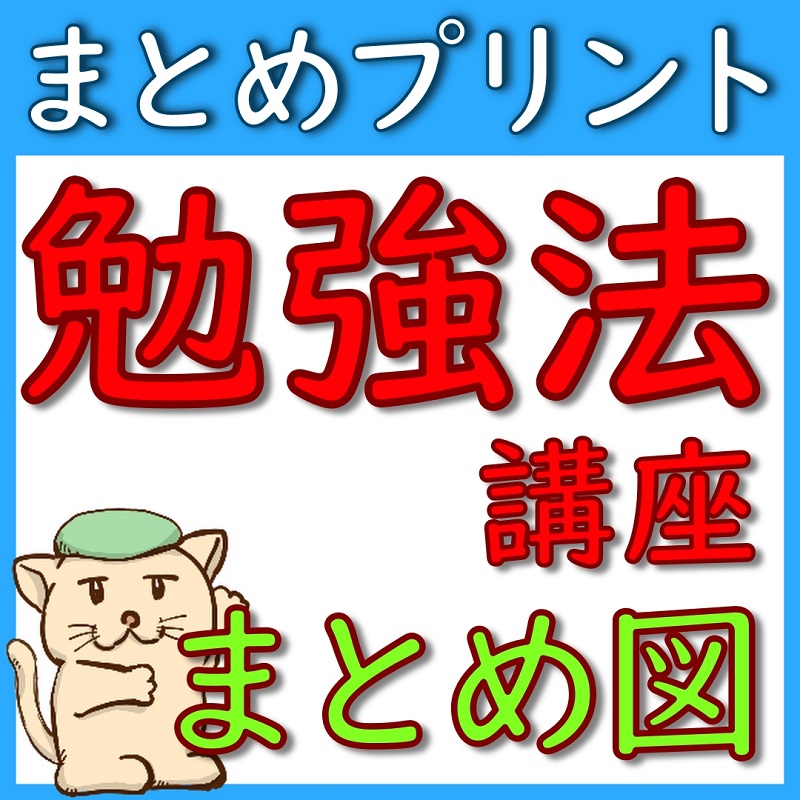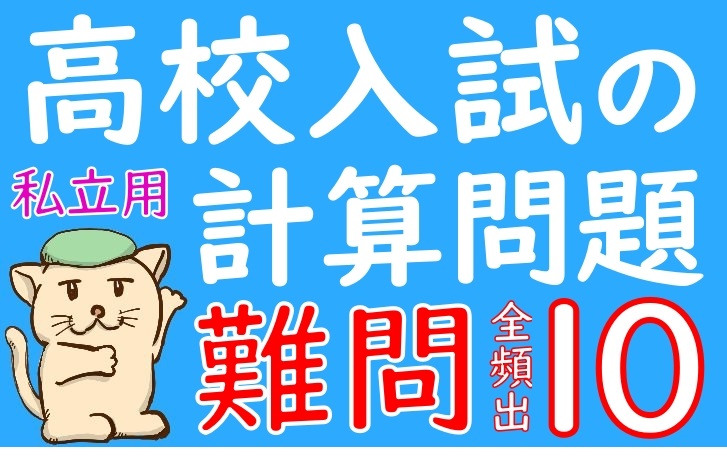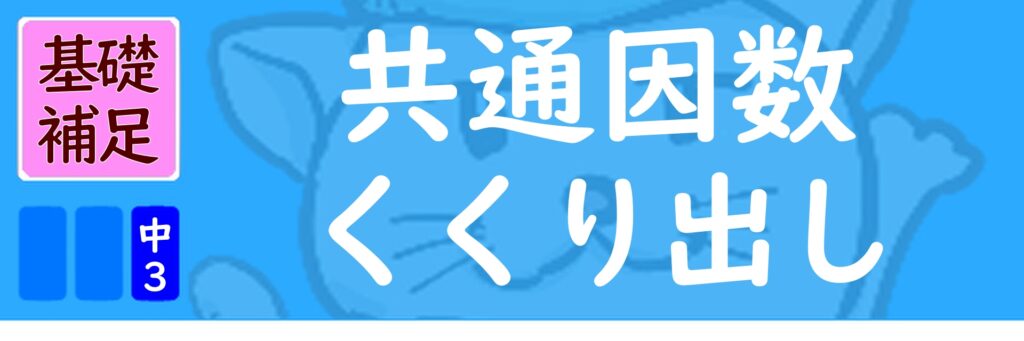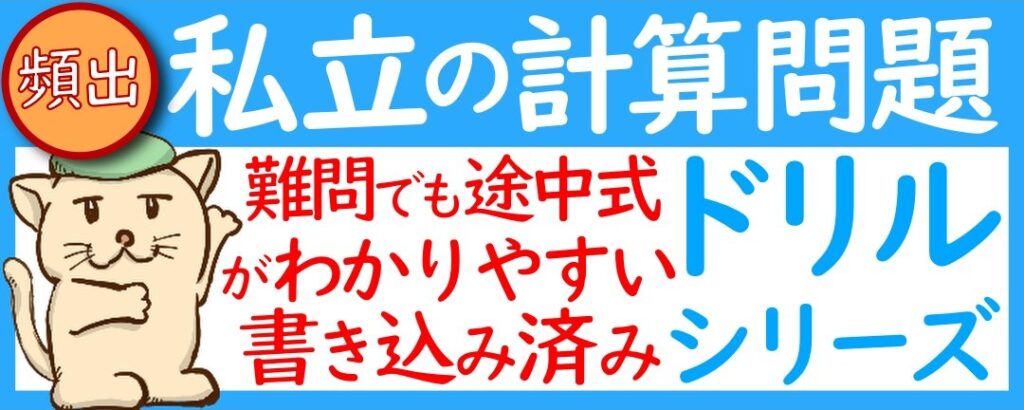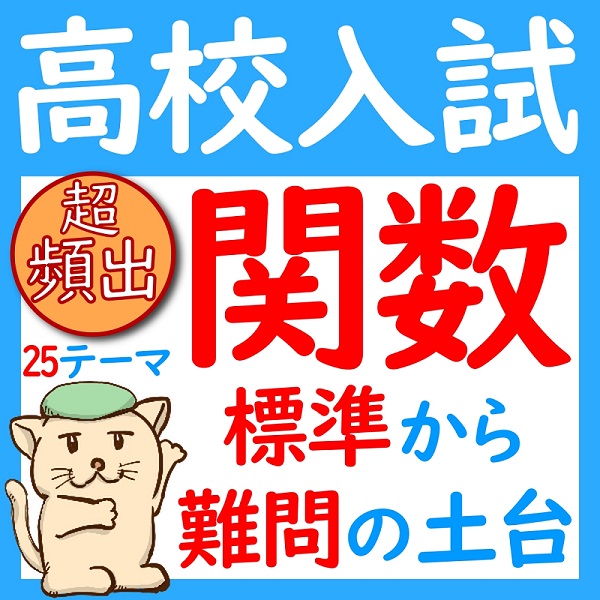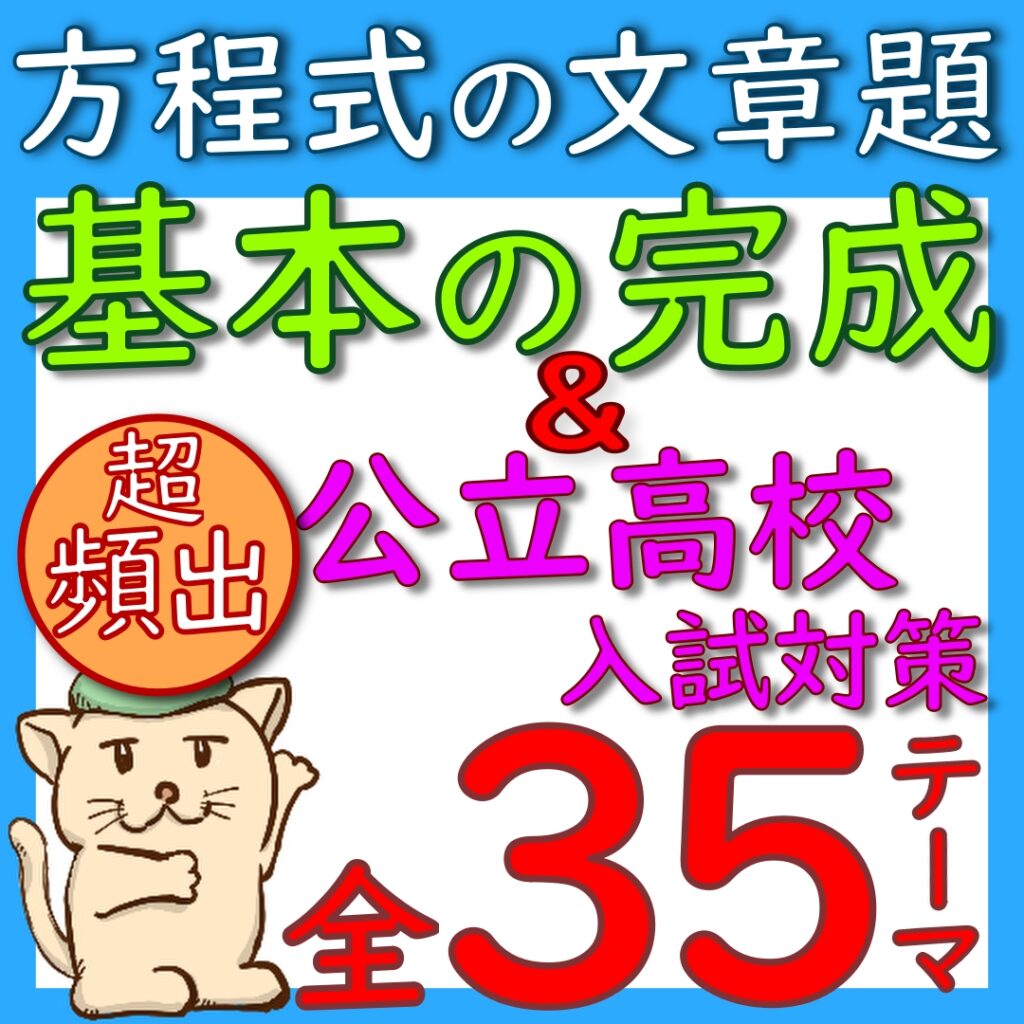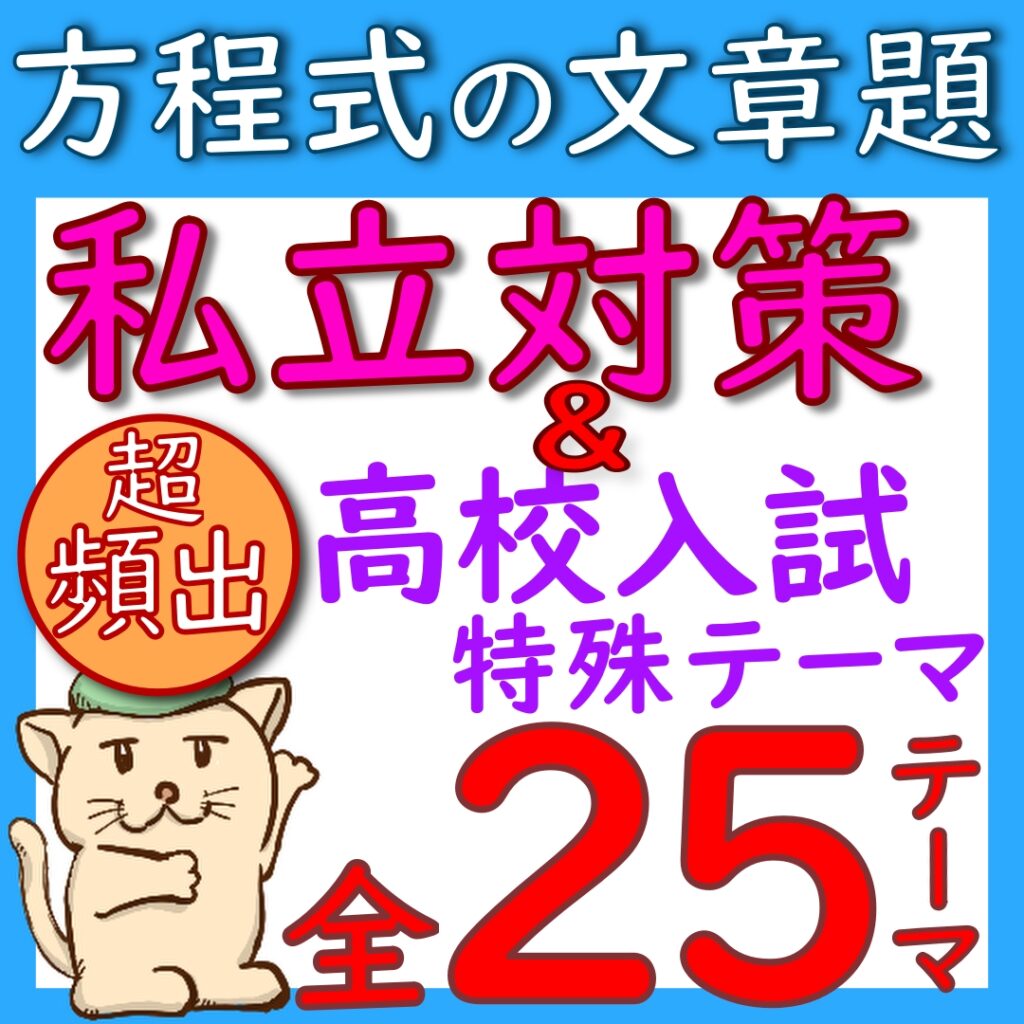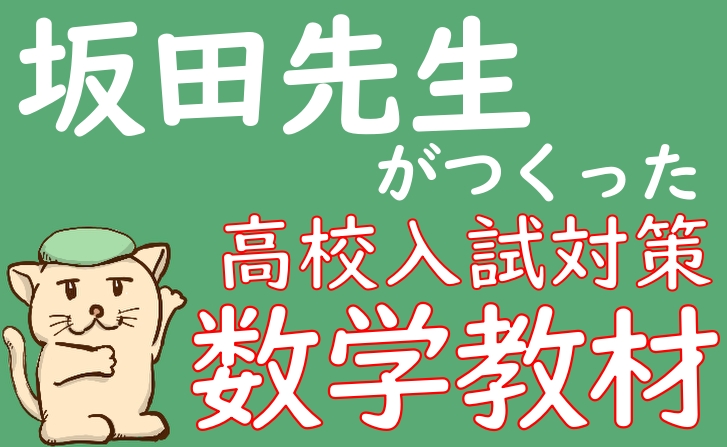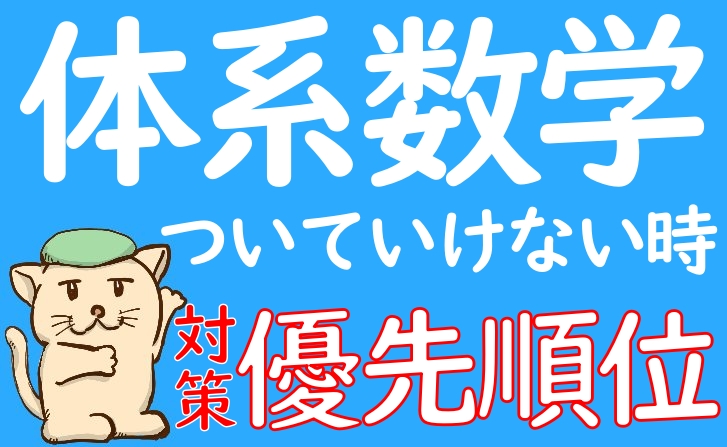



- 中高一貫の体系数学についていけない主な原因3つ
- 中高一貫の体系数学についていけない場合の具体的な対策
- 中高一貫の体系数学についていけない場合に最もやっていけない対策
中高一貫の体系数学についていけない主な原因3つ
この状況になってしまう原因として「部活や学校以外の用事以外の空き時間に、それらの疑問解消ができないほど忙しい」というケースがあります。

疑問を解消し、テスト対策のための学習時間をとることはもちろん大事なのですが、それよりも「そもそも提出物ができていない」というほどの状況であれば、次の内容が重要になります。
※基本的にはテスト対策よりも提出物をまずは優先します。(成績に直結しますので)


また、普段はそこから課題を出さずに、ある時まとめて出されるという事も多く、普段からあらかじめコツコツ解いておくということができない子には大変です。
「苦手になる負のループ」がここから始まっていると言っても過言ではありません。


このような子の場合、次の定期テスト範囲の学習に必要な(体系数学1の内容も含めた)基礎を同時に復習することになります。

現在学校で学習している内容がわからない場合は、これを同じことをするしかありません。
すなわち「次の定期テスト範囲を学習するために必要な基礎からの復習」が必要になります。
中高一貫の体系数学についていけない場合の具体的な対策

・学校からの課題は、直前にまとめて片付けるのではなく、前もってコツコツ済ませてゆく。
・わからない問題は、学校の先生または塾や家庭教師の先生に質問して、疑問解消してゆく。
・次の定期テスト範囲を学習する際に、さかのぼって学習する必要があるものも同時に復習する。

2:大学入試で数学を使う予定である



中高一貫校の偏差値は50~55
普段は課題はないが、毎週週末に課題プリントがある。
テストは定期テストのほかに、毎月小規模の単元別テストがある。
提出物ワーク:体系問題集(標準)数研出版
目標:高校の内部進学さえできればとりあえず良しとする(かつ平均点以上をねらいたい)
優先順位1:学校からの問題プリント、小テスト、週末課題の問題をマスターする。
優先順位2:体系数学の教科書の例題かつ、基礎の問題のみを反復する。
優先順位3:その例題に備わっている練習問題を反復する。
優先順位4:体系数学の教科書の章末にある「確認問題」を反復する。
やらないこと:提出物ワークの体系問題集(標準)を反復する。



・理解するのに時間がかかる。
・習得するのに時間がかかる。
・少しひねって出されると回答できないことが多い。

以上の理由により「優先順位1~4の範囲外のものは(解答を読んで意味がわからなければ)とりあえず書きうつして提出できる状態に仕上げておく」ことを、該当する生徒さんには徹底させています。


中高一貫の体系数学についていけない場合に最もやっていけない対策

・練習では解けていた問題だったのに、テスト本番では解き方を、ど忘れしてしまうことがよくある
このような子には「基礎を徹底的に反復してマスターするまでは対策範囲を広げない」ということを徹底しています。
つまり、最もやってはいけないのは「対策範囲を最初から広くしてしまい、基礎レベルの反復が不十分になってしまう」ことです。
最初から「基礎から標準レベルを対策する」のではなく。
2:基礎から標準レベルを反復する
という順序を踏むということです。


でないと「(平均点が高いテストで)練習してきたパターンの問題をすべて正解できていたら80点以上取れていたのに、(多くの計算ミスと緊張からのど忘れで)40点ほどしか取れなかった」という結果も十分ありえます。